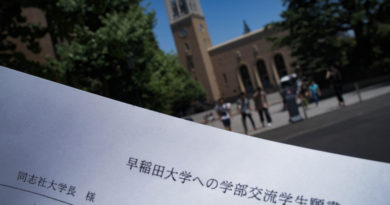同行援護支援で広がる世界 ― 視覚障がい者とともに歩む
コンテンツ
はじめに
「情報のおよそ8割は『目』から得ている」 こんな豆知識をどこかで聞いたことはないだろうか。 それほど重要な情報源である目がさまざまな理由で、見えない・見えにくくなった人々が外出時に利用できるサービスが「同行援護」である。 私の祖父は網膜色素変性症により中途失明し、このサービスを利用しては美術館や散歩へと出かけていた。その外出をワクワクしながら待ち、「美術館に行くなら〇〇さんの説明が楽しいな」などと笑いながら話していた。そんな祖父を近くで見ている一方で、駅や人混みの中ぽつんと一人佇む白杖を持った方を見かける機会が多いことが気になった。 「同行援護支援」とは、誰がどのように利用できるのか。晴眼者[1]に何ができるのか。 視覚障害の原因疾病4位[2]の加齢黄斑変性は病名にもあるように加齢が一要因だ。誰にでも起こりうる視覚障害だからこそ、誰か身近な人が、いつか自分が、使う制度かもしれないと考えてほしい。(文・写真=八木橋萌々子)
第1章 同行援護について行こう
「今日もよろしくね」その一言から、通院の同行援護が始まった。最高気温35℃。ジリジリと焼かれるような暑さのなか、焦茶色のサングラスをかけ白杖をつく小汐唯菜さん(19)と、リュックを背負い薄手のピンクのカーディガンを羽織った土井日菜子さん(20)の2人は歩き始めた。唯菜さんが白杖を握っていない左手で日菜子さんの右肘の少し上に手を添える。そこには「掴んでください」の言葉も必要とせず、そのなめらかなスピードに危うく私が置いていかれるほどだった。
唯菜さんはレーベル先天盲[3]により先天性の「見えにくさ」を抱えている。現在は、国立音楽大学の2年生として声楽を学んでいる。同行援護を知ったきっかけは、ランニングコミュニティの中での紹介だった。コンクールへの出場に利用することが多いそうだ。
そんな唯菜さんを支える日菜子さんも同じく国立音楽大学で学ぶ2年生だ。唯菜さんとは英語の授業で出会った。視覚障がい者をガイドする「手引き」の経験はなかったものの、学校内での介助を手伝っていた。友人としての介助から、資格を所有したガイドヘルパーとしての介助を志したのは唯菜さんからの紹介がきっかけだった。同行援護の研修後、日菜子さんの介助への意識は大きく変わった。「唯菜に(今までのガイド方法を)申し訳ないなと思いました。それまで思ったことなかったんですけど、怖くなりました。私の言葉が、その人の世界になるってことなんだなって」
前日にあった出来事、サークルの話、家族の話をしながら彼女たちはバスを待つなかで、取材の緊張と暑さにやられてしまった私に唯菜さんは塩分チャージを差し出してくれた。2人の明るさや優しさに触れるなかでトラブルが起きた。バスが来ないのだ。そこで日菜子さんは代替案として電車での移動を調べ始めた。現在の時間と電車の時間や間隔、乗り換えの時間など、一つ一つの情報を整理し順序立てて唯菜さんに伝える。日菜子さんが決めるのではなく、唯菜さんに判断を任せているのだ。
電車に乗っている間も会話の合間に、乗り換えのルートを検索しスムーズに案内できるように日菜子さんは準備をしていた。唯菜さんも前回の記憶や事前情報を日菜子さんと共有し2人で病院へと向かっていった。
病院からの帰り道、日焼け止めを買いにドラッグストアへ向かった。「ビオレの日焼け止めで全身に使えるようなもの」唯菜さんが求めるものを、日菜子さんが目となり探す。クリームタイプやミストタイプなど、メーカーを絞っても数種類ある。7種類ほどあるなかから口頭での説明で3種類に絞り、大きさやタイプを唯菜さんに触れて確認してもらっていた。2人の姿は日焼け止めを選ぶ友人同士のようにも見えつつ、日菜子さんの細やかな気遣いがあった。彼女の細やかな気遣いは、カーディガンにも隠れていた。同行援護では肘を掴んでもらい案内するため、利用者が掴みやすいように、夏は薄手の羽織もの、冬は分厚くないコートを着るよう心がけているそうだ。こうした配慮も同行援護資格取得の研修で学ぶことができる。
その日の同行援護の中で、唯菜さんが日菜子さんに一度だけお願いをしている場面があった。改札を通るときだ。はじめは日菜子さんがはじめに改札を抜け、彼女に続いて唯菜さんが通る形をとっていた。その順番を逆にするよう唯菜さんは頼んだのだ。見えにくい唯菜さんにとって手のひらよりも小さい場所を探すことは難しい。そのため、日菜子さんが後ろにつくことで唯菜さんの手を改札機に導くことができ、スムーズに通ることができるのだ。各人それぞれ、ガイドヘルパーに求める手引きの仕方があり、ガイドヘルパーは各人の見え方に対応する。友人ではなく同行援護であるからこそ、気兼ねなく要望を伝えることができるのではないかと感じた。
唯菜さんは買い物帰りに、「70代ぐらいのヘルパーさんだと、買い物のおすすめも教えてくれるんです」と楽しそうに話してくれた。「40代の男性のヘルパーさんには、おすすめのおつまみを教えてくれたり!いろんなヘルパーさんと話して世界が広がる感じです」唯菜さんはそのときの会話を思い出したのか笑いながら語った。そして、「世界が広がる」と話したのは日菜子さんもだった。日菜子さんは同行援護でプールやゴルフに参加したことがあるそうだ。自分1人では飛び込めない世界に、利用者の方の誘いで飛び込む。日菜子さんはわくわくを隠しきれない様子で、楽しかった同行援護の経験をきらきらした笑顔で話してくれた。日菜子さんの「(ヘルパーの)言葉が世界になる」というのは、同行援護のその一瞬一瞬の情報だけではなく、ガイドヘルパーの持つ知識や感じ方が利用者の世界の一部になるのだ。
「9月にコンサートあるんです!」とチラシをくれた唯菜さん。「(同行援護の研修を受けて)怖くなりました」と言いながらも、スムーズに介助し、広がる世界に飛び込む日菜子さん。自分よりも年下の2人から思いがけず得た活力は大きなものだった。

第2章 同行援護とは
同行援護とは「視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の主務省令で定める便宜を供与すること」[4]と、障害者総合支援法第5条4(旧・障害者自立支援法)にて定められている。
「外出時」に含まれる移動とは、習い事や散歩などの余暇活動、買い物、通院である。ただし、通勤通学には利用できない。
同行援護の土台となった制度は、移動支援という地域生活支援事業の一つである。地域生活支援事業とは、障がい者自身が住む自治体の裁量によって事業にかける経費が決められるため、自治体間の程度の差が大きく開いていた。こうした現状を日本視覚障害者団体連合をはじめとした、当事者らが声を上げ続けたことで、2011年10月に義務的経費による個別給付として同行援護が定められた。これにより全国で制度の基準が同行援護アセスメント票により統一され、さらに移動支援では補いきれなかった「情報の提供」を目的として明記されることとなった。
同行援護利用の流れ
では、同行援護を利用するためにはどうすればいいのか。大まかに以下のようなステップが必要となる。[5]

まず同行援護を利用するには基本的に、身体障害者手帳(以下、障害者手帳)の所持が前提である。[6]医師の判断をもとに障害者手帳の取得を申請する。障害者手帳取得後、市役所などの窓口で同行援護サービスの利用申請を申し出る必要がある。
申請後以下の同行援護アセスメント調査票[7]をもとに同行援護のサービスの必要性の調査を受ける。

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaiseihou/dl/sankou_110926_03_4.pdf
このとき、身体介護を伴う同行援護を希望する場合には障害支援区分認定調査も行われる。これらの審査終了後、サービスの利用計画案を計画専門福祉サービスと相談、もしくは利用者本人が作成した案の提出が求められ、行政の担当者はその計画案を踏まえて同行援護の支給を判断する。支給の決定までには同行援護の利用申請からおよそ1~2ヶ月を要する。受給者証を受け取ったのち、同行援護事業所との契約を結ぶことで、サービスの利用が可能となる。
同行援護を利用する際にかかる利用者の負担費用は、応能負担となる。基本的に市町村民税所得割の額によって、負担上限月額が定められいる。月額の使用料が負担上限金額を下回る場合は、サービスにかかった費用の10%が利用者の負担となる。費用の計算方法は以下の図に示されているように、単位数での計算となる。1単位あたりの金額は地域によって異なるが、東京都23区にある事業所では1単位あたり11.2円と定められている。[8]障害支援区分などの加算がない場合、2時間の外出での利用で利用者が負担する金額はおよそ630円である。この金額に加え、ガイドヘルパー分の映画チケット代などのイベント代金は利用者の負担となる。

https://www.mhlw.go.jp/content/000759623.pdf
こうした複雑な申請や利用方法を乗り越え、同行援護を活用している人は少ない。厚生労働省の調査によると、障害者手帳を発行している視覚障がい者数は2022年度末時点で32万766人。[9]同行援護の利用者数は2023年4月に国民健康保険団体連合会から発表された実績では2万6584人にとどまる。[10]
第3章 同行援護資格取得の流れ
同行援護について取材を進めていくなかで、実際に私は資格取得を目指すことにした。そして、2024年12月18日~22日の5日間、日本ブラインドサッカー協会(以下、JBFA)主催の同行援護従業者養成研修に参加することができた。JBFAではmeetme-X(ミートミークス)というスマートフォンアプリを利用した、同行援護サービスを運営している。
私がJBFAを見つけたのは東京都福祉局のホームページだった。[11]他にも「同行援護 研修」と検索すると、各事業所のホームページなどにアクセスすることができる。
「(利用者の方が)自己判断、自己決定できるように伝えることが重要です」
講師の方々がはじめに伝えたこの言葉を、そのとき私は安易に当たり前のことじゃないかと感じてしまった。講義が進むにつれ、これがいかに難しいかを知ることになった。
5日間の研修のうち、3日間はオンラインで行われた。ブラインドサッカー観戦をきっかけに同行援護に興味を持った人や、専門学生、たまたま同行援護について知り応募した大学1年生など、私を含め9名が参加した。日中働いている人も「オンライン講座だったからこそ申し込めた」と他の事業所の研修を諦めたことも話してくれた。
座学編
オンライン講座では、同行援護での基本姿勢や意識の面だけでなく、視覚障害の疾病ごとに異なる見え方や、配慮すべき点の具体的な解説が行われた。例えば糖尿病網膜症の場合、視覚障害に加え手や足の神経障害も伴うこともあり、痛みに鈍感になるため怪我に気づかず感染症にかかるリスクが高まる。そのため、同行援護中の怪我だけでなく、会ったときに切り傷などがないかを確認する必要がある。
また、講師が実際に経験した現場の写真やイメージ画像を提示しながら、「利用者が自己判断できる情報提供」のためにどのように説明するかを話し合った。
例えばこの画像。あなたならどう説明し、利用者と歩んで行くだろうか。 
私が講義を受けていたときの回答は「芝生の真ん中に茶色いタイルの道が続いています、左右に道が曲がりくねっています」しかし、「利用者が自己判断できる情報提供」にはまだ不十分だった。「どちらの道の方が歩きやすいですか?」などと相手に聞く一言が重要だった。私の回答では、タイルの上では凹凸が多く、歩きづらさが加わることには気付いたものの、「タイルを歩くのが普通」という先入観によって、利用者の選択を狭めてしまっていた。
利用者によっては歩き慣れた場所であれば、迂回するスロープよりも数段の階段のほうが良い場合もある。ガイドヘルパーの先入観で判断せず、視覚障がい者の「目」となる意識が重要である。
実践編
後半2日間は対面講座となり、屋内や新宿周辺の屋外での研修が始まった。2人1組となり、1人がアイマスクをつけ利用者役を、もう1人がガイドヘルパーとして利用者役を案内する実践形式だった。
同行援護の業務の重要なものとして、コミュニケーションのサポート(代筆・代読・利用者の支援)が挙げられる。私が講義の中で最も難しさを感じた業務だった。パスポートの発行など、視覚障がい者本人の署名を求められる場合がある。利用者の手を誘導したり、欄の枠組みを手で示したりしながら小さな欄に名前が収まるようサポートする。その方法に正解があるわけではないため、利用者役とガイド役を交互に経験する中で、受講生間で自然とアドバイスをし合いながら研修は進んだ。
最終日にはいよいよ屋外での研修が行われた。JBFAの事務局(JR大久保駅)周辺から新宿三丁目周辺を歩くなかで、階段やエスカレーターを利用した上り下りに加えコンビニでの買い物も実践した。コンビニでの買い物では、自分も初めて行く場所で、どこに何が売っているのかも把握できていない状況で案内する難しさがあった。

私はその実践のなかで、聴覚などの感覚がより敏感になった気がした。車のエンジン音、歩道の若干の傾斜や緩やかな登り道など、目からの情報が遮断されているだけで、少しの変化を不安に感じてしまうのだ。アイマスクをつけて外に出なければわからない体験だった。「視覚からの情報は全体の約80%を占める」ことの不安を理解したつもりでいた自分を恥ずかしく思った。

5日間の研修を通して、第1章の土井日菜子さんのガイドがどれほどスムーズかつ配慮が尽くされたものだったのかを痛感した。難しさや不安を感じる一方で、同行援護が視覚障がい者の快適な外出にさらに活用されてほしいという思いが強くなった。
若いガイドヘルパーを
同行援護中の提供する情報のポイントは大きく3つある。
① 安全に関する情報
② メンタルマップ[12]づくりに必要なランドマークなど
③ 空の色や花などの季節の情報
特に③は快適で楽しい外出のために必要不可欠である。利用者の「目」としてともに歩むガイドヘルパーは現在不足していると同時に高齢層が多い。利用者の中には、スポーツの練習や観戦などを楽しみたい人も多くいる。それらのニーズに応えるためにも、体力のある若年層の力が必要になるだろう。
この記事を読んだあなたにも、誰かの世界を広げる1人になってほしい。
第4章 抱える数々の課題
成立から13年以上が経ったにもかかわらず、利用者数が少ない理由には、利用者と事業者の両側面からの課題が存在する。
利用者の声

同行援護の利用状況や利点などについて、話を聞くために日本視覚障害者団体連合へ向かった。JR高田馬場駅からおよそ600m、歩いて10分ほどの道のりの足元には途切れることなく点字ブロックが続いていた。その点字ブロックが終わった目の前に日本視覚障害者団体連合の建物がある。私はそこで工藤正一さんと吉泉豊晴さんに話を聞くことができた。
工藤さんは32歳の時にベーチェット病[13]にかかり37歳で失明。吉泉さんは先天的に右目のが見えず、12歳で網膜剥離を患い全盲となった。お二人とも失明後労働省での勤務を経験し、現在は日本視覚障害者団体連合で活動をされている。
同行援護という全国で統一された制度が成立したことで、遠方利用が可能になったことや個別給付が可能になったことで、移動支援だけでは補いきれなかったサービスが提供されるようになった。しかし、視覚障がい者の多くが「利用しにくい」と感じている点は二つある。「予約」と「車での移動」だ。
吉泉さんが利用する事業所の場合、1週間前の予約が原則として求められ、前日の予約は難しい。急な外出の予定があった際には、利用できないこともある。
また公共交通機関での移動が原則とされている同行援護だが、利用者からの「車での移動」の要望は多いと工藤さんは語る。しかし、その対応は事業所によって異なる。ガイドが利用者を乗せて車を運転するには、福祉有償運送[14]など行政からの認定が必要となり、さらに運転中はガイド時間として算定できない。そのため「車での移動」を業務として提供している事業所は限られている。その一方で、利用者は公共交通機関の利用には同行援護を利用しないことも少なくないと言う。例えば工藤さんが視覚障害に関するイベントに参加したとき、電車等の利用では駅員が、駅から会場まではイベント主催者がサポートをしてくれる。つまり、公共交通機関の少ない場所でこそ同行援護が求められると言える。
事業所から見た同行援護
利用者からの要望が上がる一方で、各事業所は大きな課題に直面している。「ヘルパー不足」だ。
ヘルパー不足の要因として、研修へのハードルの高さが挙げられる。同行援護のガイドヘルパーとして活動するには、資格を取得し「プロ」として時給が発生する仕事となるため、研修受講が必須である。自治体によっては3000円ほどで受講できたり、事業所によって学生割引が適応できることもあるが、平均的な研修費用は3万円前後である。さらに費用の高さだけでなく、研修時間も課題がある。同行援護従業者養成研修は、自治体や各都道府県が指定した事業所が厚生労働省が告示したカリキュラム[15]をもとに行われている。講義12時間以上、さらに実技演習8時間以上の計20時間を必要とする研修は、平日の日中などに組まれることも多く、社会人や学生は受講が難しい。
こうした課題について、同行援護事業所mitsukiの代表である高橋昌希さん(33)に話を聞くことができた。高橋さんが運営するmitsukiでは障がい者スポーツを楽しみたい利用者の方も多く、若い世代を意識しているという。mitsukiでは300名ほど登録しているガイドヘルパーの方のうち、20代から30代の方が合わせて100名以上、約40%を占めている。mitsukiの研修では、学生ボランティアや大学のバリアフリーサークルなど学生をターゲットとしている。その甲斐もあってか、土井さんのように利用者の方と水泳やゴルフを楽しみながらガイドをするといった、利用者のニーズに合わせた同行援護に対応することができる。
事業所を運営しながら課題を感じている点として、高橋さんは自治体間の差について指摘してくださった。同行援護は自立支援給付であり、介護給付費として扱われる。受給者証の発行に伴い、市町村単位の自治体が利用者に1ヶ月単位で上限時間を設定し支給する。先述した同行援護の成立背景において、個別給付の要請により移動支援だけでなく同行援護が確立されたと述べた。同行援護アセスメント調査票など全国一律の判断基準が導入されたものの、実際のところ差が生じているという。事業所間では、A自治体は利用者の声を聞き柔軟に対応してくれるが、隣のB自治体では50時間以上は増やしづらいといった情報が共有されることもあるという。こうした自治体間の差により、複数自治体をまたいだ遠方利用へのハードルなどまだまだ改善点は残されている。
さらに日本ブラインドサッカー協会が運営する同行援護事業所の担当者である岡本邦夫さんは、医療機関と制度の結びつきの弱さを指摘した。身体障害者手帳や受給者証の取得のためには医師の診断書が必要になる。しかし、医師が障害者手帳の取得を促すことはあっても、「その先にどういった制度が存在するのか」までを病院が紹介しきれていないケースを聞くのだと残念そうに岡本さんは語った。視覚に不安を覚えた人が一番に駆け込む先は眼科である。その病院と制度をより一層連携を深めることで、障害者手帳の発行に消極的な人が少しでも前向きに捉え適切なサービスにつながることができるのではないだろうか。
65歳問題
社会保障制度には原則として保険優先の考えがある。そのため、65歳以上の障がい者はサービス内容や機能によっては障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合、介護保険にて提供されるサービスを優先して受けることを原則として求められる。この制度間の優先順位によって生じる「生きづらさ」は「65歳問題」と呼ばれている。ただし介護保険サービスの中に、障害福祉サービスに相当するサービスがない場合は障害福祉サービスを受けることができる。基本的に同行援護はこれに該当する。しかし、給付時間や案内するサービスの内容は自治体により異なるのが現状だ。「65歳問題」の具体例について、日本視覚障害者団体連合の工藤さんと吉泉さんから伺うことができた。
たとえば…
Aさん(66)が通院のために同行援護を利用しようとしたとする。しかし介護保険サービスを優先的に使用することを自治体に促されたAさんは皆保険サービスの「通院介助」を利用することとなる。通院時に同行援護を利用すると、病院内の移動や問診票記入の手助けなど病院の中に入ってからも支援が行われる。その一方で通院介助では病院と家の往復での援助に限られてしまう。Aさんは65歳を過ぎ、いままで受けられていたサービスが急に受けられなくなってしまったのだ。
また実際の事例として費用負担の増大が挙げられた。介護保険サービスへの移行が求められたことにより、代替できるサービスの分、障害福祉サービスの供給時間が減ることになるのだ。しかしながらAさんのように本来代替になっていないサービスまで自治体の裁量により考慮されてしまうため、実質的なサービス時間を減らされてしまうのだ。さらに障害福祉サービスは支払い能力に応じた応能負担であるのに対し、介護保険サービスは受けたサービス量に対応する支払いが求められる応益負担である。そのため一定量かつ65歳以前と同じ量のサービスを受けると考えると、必然的に負担額が増えてしまうのだ。
乗り越えるために
こうした65歳問題の背景について、視覚障害リハビリテーション協会に所属する吉野由美子さん(76)に話を聞いた。
私をマンションのエントランスで迎えてくれた吉野さんは電動車椅子に乗っていた。彼女は先天性白内障による弱視と大腿骨の発育不全による肢体障害を抱える重複障がい者である。現在は視覚障害リハビリテーションの普及活動に尽力している。

65歳問題の背景には各制度設立の際に掲げられた理念の違いがあると言う。障害者総合支援法は、障害ごとに違うニーズに適合したサービスの提供を目的としている。その一方で、介護保険制度は身体的介護の提供を重視している。介護サービスを受けることができるのは「家事や身支度等の日常生活に支援が必要になった状態(要支援状態)になった場合」[16]であり、要介護認定度の判定が必要である。要介護認定の基準は、視力調査などの身体調査だけではなく、入浴や排泄、家事の援助など日常生活に関わる場面が大きい。「視覚障害は情報障害である」。これは工藤さん、吉泉さん、高橋さん、吉野さん、岡本さんら、みなさんが繰り返し伝えてくれた。ここに大きな違いがある。視覚障がい者の一部は、自宅など日常生活を行うような慣れ親しんだ場所では介助を必要とせず行動することができる。そのため、「日常生活の可否」を基準とする要介護認定では測ることができない。この制度的背景を視覚障がい者自身やその家族、窓口である自治体の職員が完全に理解することは難しい。そのため、慣例的に65歳になると介護保険への移行が促され、移行した後に求めるサービスとのずれが表出することになる。
しかし、この65歳問題は自治体の福祉課に通達を持っていくことで改善が見込めるのだと吉野さんは説明してくれた。「(制度を)受けるかどうかの選択肢はこちらにある」吉野さんは力強く語った。当事者として制度を学び知っていくことの重要性を話してくださった。
おわりに
日本眼科医会の研究によると、2007年時点で失明・弱視合わせて視覚障がい者数は164万人に上ると推定されている。[17]その一方で身体障害者手帳を所持している視覚障がい者は2022年度末時点で32万766人。この二つの数字の乖離には身体障害者手帳交付認定・発行へのハードルの高さや抵抗感、さらに老化による視力低下として弱視を障害として認識しづらい傾向にあると、工藤さんはおっしゃった。
さらに「制度の中で生きていかないといけない」。工藤さんは苦々しい思いを口にした。利用可能なサービスの提示や、福祉制度が不十分であるために制限が生じてしまう現状がある。同行援護だけでなく、社会にはさまざまな障害を抱えいまだに適切なサービスにアクセスできていない人がいる。私たちが自分の今の世界から少し視野を広げ、制度について学んだり、まちで困っている人に声をかけたりすることは、必ずいつか誰かの助けになるのではないだろうか。
注
[1] 視覚に障害がない人 [2] https://www.nichigan.or.jp/public/disease/name.html?pdid=52 [3] 生後より重い視力障害を示し、視線が合わず、まぶしがったり、黒目が振り子のように動き続ける振子様眼振(ふりこようがんしん)がみられ、対光反射(光をうけたときに瞳孔が小さくなる反射)が弱い、または消失する先天性の病気http://www.japo-web.jp/info_ippan_page.php?id=page19
[4]平成25年4月1日より、障害者自立支援法は障害者総合支援法に改正https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa7574&dataType=0&pageNo=1
[5] https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/riyou.html [6] 障害者総合支援法の対象となる疾病の場合手帳がなくともサービスの利用が可能 [7]https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaiseihou/dl/sankou_110926_03_4.pdf [8] https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8493&dataType=0 [9] https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/gyousei/22/dl/kekka_gaiyo.pdf [10] https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001147024.pdf [11] https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/fukushi/doukouenngo1115 [12] 頭に思い浮かべた目的地までの経路・地図 [13] 免疫の異常によって全身の血管に炎症を起こす自己免疫疾患。症状の一つに眼の炎症が見られることがあり、ぶどう膜炎が主である。眼の内部に発作的に炎症が起こり視力に大きな影響を与える場合がある。https://www.nichigan.or.jp/public/disease/name.html?pdid=22
[14]NPO法人や社会福祉法人などが、障害者や高齢者など一人で公共交通機関を利用することが困難な方を対象に行う、ドア・ツー・ドアの有償移送サービスhttps://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/machizukuri/yuusyou
[15]厚生労働省の告示により、カリキュラム内容は2025年4月1日より改正 https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001225679.pdf [16] https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou/15kourei/sankou3.html [17] https://www.gankaikai.or.jp/info/kenkyu/2006-2008kenkyu.pdf